
猿 橋(さるはし)
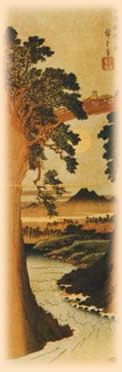
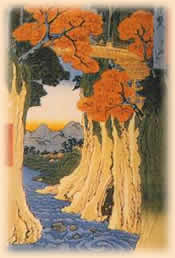 伝説によると、百済の渡来人志羅呼が推古天皇の代に猿が川を越えるのにヒントを得て、橋を架けることに成功したという。
伝説によると、百済の渡来人志羅呼が推古天皇の代に猿が川を越えるのにヒントを得て、橋を架けることに成功したという。
架橋の方法は谷が深く橋脚を立てることができないため、両岸から刎木を四段に差出し、たがいにせり持たせた上に橋桁をのせる構造となっている。その構造が特異なことから古くより知られ、峡谷の自然美と人工の構造美が調和する名橋として国の名勝に指定される。
文明19年(1487)聖護院道興が小仏峠を越えて郡内に入り、当地を訪れて「猿とて川の底千尋にをよび侍るうへに、三十余丈の橋をわたして侍りけり」と記し、また、昔猿が架橋した話、朽損の際は国中の猿飼が勧進したことなどの伝承を記し、和歌三首、漢詩一編を詠じている。(廻国雑記)
「勝山記」によると、小山田越中守信有は永正17年(1520)に猿橋を架替え、天文2年(1533)の焼失後、同9年に架橋するなどその維持に努めている。
 近代以降は、明治33年(1900)、昭和26年にそれぞれ架替えが行われてきた。甲州街道の要衝として、江戸期には荻生徂徠の「峡中紀行」、安藤広重の甲陽猿橋之図などで広く紹介され、俳句・和歌・漢詩などにも詠まれて有名となった。
近代以降は、明治33年(1900)、昭和26年にそれぞれ架替えが行われてきた。甲州街道の要衝として、江戸期には荻生徂徠の「峡中紀行」、安藤広重の甲陽猿橋之図などで広く紹介され、俳句・和歌・漢詩などにも詠まれて有名となった。
![]()
![]()
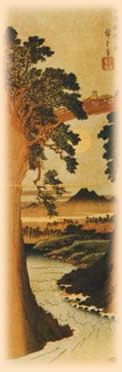
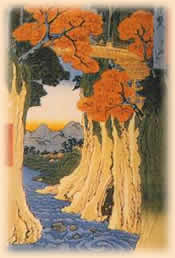 伝説によると、百済の渡来人志羅呼が推古天皇の代に猿が川を越えるのにヒントを得て、橋を架けることに成功したという。
伝説によると、百済の渡来人志羅呼が推古天皇の代に猿が川を越えるのにヒントを得て、橋を架けることに成功したという。 近代以降は、明治33年(1900)、昭和26年にそれぞれ架替えが行われてきた。甲州街道の要衝として、江戸期には荻生徂徠の「峡中紀行」、安藤広重の甲陽猿橋之図などで広く紹介され、俳句・和歌・漢詩などにも詠まれて有名となった。
近代以降は、明治33年(1900)、昭和26年にそれぞれ架替えが行われてきた。甲州街道の要衝として、江戸期には荻生徂徠の「峡中紀行」、安藤広重の甲陽猿橋之図などで広く紹介され、俳句・和歌・漢詩などにも詠まれて有名となった。