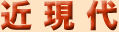
宝鉱山(たからこうざん)
 宝鉱山の鉱床は硫化鉄鉱の大塊鉱で、明治5年、宝村の岩村善五衛門が赤棚沢で鉱塊を発見したのに始まるといわれている。
宝鉱山の鉱床は硫化鉄鉱の大塊鉱で、明治5年、宝村の岩村善五衛門が赤棚沢で鉱塊を発見したのに始まるといわれている。
その後、明治23年4月、村民安田盈房ら有志により、大幡山字本社沢銅鉱を開抗するため「鶴鳴組」と称した組合を結成して採掘したが長続きせず、明治27年、東京の鈴木政吉が稼行するに及び坑道の開さくを進め、製錬など試みたが成功せず、明治31年には石井千太郎の所有に帰したが、同36年に至り三菱合資会社に譲渡した。
三菱の鉱業経営は、日清、日露の両戦争を経過して、我が国の産業は重工業化に向って次第に転換した時期で、それに対応して大きな伸展を迎えた。
第2次世界大戦中は軍需工場の指定を受け、食糧事情の苦しさの中で増産をつづけながら終戦を迎え、三菱金属鉱業宝鉱山と改め経営をつづけたが、貪鉱となり経営が悪化したため、昭和45年10月、採掘80年にわたる宝鉱山は閉山した。
中央線笹子駅までの鉄索工事は、明治41年に着工し、42年に完成した。
- 【詳しく知りたい人】
- 都留市史 資料編 近現代 1993 都留市史編纂委員会
都留市史 通史編 1996 都留市史編纂委員会
![]()
![]()
 宝鉱山の鉱床は硫化鉄鉱の大塊鉱で、明治5年、宝村の岩村善五衛門が赤棚沢で鉱塊を発見したのに始まるといわれている。
宝鉱山の鉱床は硫化鉄鉱の大塊鉱で、明治5年、宝村の岩村善五衛門が赤棚沢で鉱塊を発見したのに始まるといわれている。