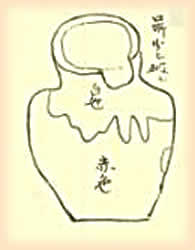徳川家康(とくがわいえやす)
 天文11年(1542)生まれ。江戸幕府初代将軍。
天文11年(1542)生まれ。江戸幕府初代将軍。
三河岡崎城主松平広忠の長男。幼名竹千代、初名元信・元康のち家康と改めた。院号安国院。6歳の時尾張の織田信秀、次いで駿河の今川義元の人質となる。永禄3年(1560)桶狭間の戦で義元が戦死してから岡崎に帰り、今川氏を離れ、永禄5年(1562)織田信長と結び三河を平定。永禄11年武田信玄と今川氏の所領を折半することを約し、信玄が駿河にはいると同時に家康も遠江にはいり、ついにこれを占領。この間松平を徳川と改姓。
元亀元年(1570)居城を浜松に築いて移り信長を助け、近江姉川に浅井・朝倉の連合軍と戦って大勝したが、元亀3年(1572)信玄と三方ケ原に交戦し大敗した。
しかし信玄の死後、天正3年(1575)信長とともに信玄の子勝頼を長篠に破り、天正10年にはついに武田氏を滅ばして、駿河をあわせ、また、信長の死後は甲斐を占領した。
その後、天下統一をめざす豊臣秀吉をおさえようと信長の子信雄を利用して兵を起し、小牧・長久手で秀吉と争ったが、信雄が秀吉と和睦ししたので和睦。以後秀吉の天下統一に協力し、天正17年秀吉に従って後北条氏を小田原に攻め、後北条氏の故地関八州を与えられ、江戸を居城とした。
秀吉の死後慶長5年(1600)関ケ原に石田三成を破り対抗勢力を一掃、慶長3年(1603)征夷大将軍に任ぜられ,江戸幕府を開いた。
慶長10年、将軍職を秀忠に譲り大御所と呼ばれ、駿府に引退したが、なお大事はみずから決し,大坂冬夏の両陣で豊臣氏を滅ほし,名実共に天下を統一して幕府の基礎を固めた。
元和23月太政大臣に任ぜられ、死後はじめ久能山、次いで日光山に改葬された。
家康は、天正17年(1589)9月26日鳥居元忠の居城のある谷村に入り都留郡を巡検した。
この時、羽根子の長生寺を訪れたほか、長安寺にはこの折り拝領した茶壺が今も伝えられている。
この家康が立ち寄った鳥居元忠の館跡には、東照宮が祀られていたが、これは現在勝山城址の山頂に移されている。
- 【詳しく知りたい人】
- 『甲斐国志』 第二巻 古跡之部 雄山閣
『検証両谷村』 2000 なまよみ出版

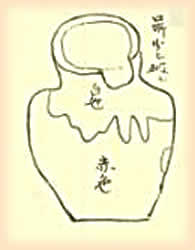
 天文11年(1542)生まれ。江戸幕府初代将軍。
天文11年(1542)生まれ。江戸幕府初代将軍。