![]()
![]()
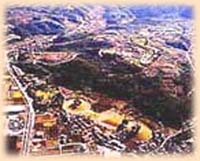 4世紀になると前方後円墳などの墳丘墓が出現するが、すでに3世紀後半に、畿内から瀬戸内海沿岸さらに北九州におよぶ地域に、それぞれ地域色を持って登場する。
4世紀になると前方後円墳などの墳丘墓が出現するが、すでに3世紀後半に、畿内から瀬戸内海沿岸さらに北九州におよぶ地域に、それぞれ地域色を持って登場する。
古墳は、その後急速に分布範囲を拡大し、4世紀中葉から後半には南九州から東北地方南部に、さらに5世紀には東北地方の中部にまで古墳が造られるようになり、7世紀にいたるまで古墳造営がおこなわれた。弥生時代の終焉となった3世紀末ないし4世紀初頭から7世紀までを古墳時代と呼んでいる。
弥生時代にはじまった水稲農耕は、鉄器の普及、耕地の拡大、灌漑技術の発達などによって、経済力が上昇し、各地に豪族が台頭するようになり、これら地方豪族はしだいに畿内の大和政権に組み入れられていた。
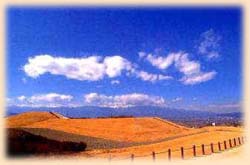 山梨県内でも、中道町東山とその周辺には、上の平遺跡の方形周溝墓群に見られるように、大規模な墓を営んだ集団の存在が明らかであり、また、4世紀中葉から後半期には銚子塚古墳や丸山塚古墳など巨大な前方後方墳や円墳などが造営され、同地域の豪族が、畿内の大和政権と結びついて甲斐の支配権を確立したことを物語っている。
山梨県内でも、中道町東山とその周辺には、上の平遺跡の方形周溝墓群に見られるように、大規模な墓を営んだ集団の存在が明らかであり、また、4世紀中葉から後半期には銚子塚古墳や丸山塚古墳など巨大な前方後方墳や円墳などが造営され、同地域の豪族が、畿内の大和政権と結びついて甲斐の支配権を確立したことを物語っている。
この中道町東山一帯は、「東海道から甲斐に入る古い道が、静岡県富士宮市から富士山麓西部~精進湖~右左口というルートであった」(末木健「遺跡の分布」『山梨県史』資料編1)とされ、ちょうど甲府盆地の玄関口となっていたのである。4世紀から5世紀に入ると、八代町の岡銚子塚古墳、三珠町の王塚古墳、大塚古墳などのように周辺地域にも前方後円墳が造られるようになり、6世紀以降はさらに甲府盆地から北巨摩地域、大月・上野原町の鶴川流域にも古墳が造営されるようになった。
 富士北麓では、古墳の存在は認められないが、桂川流域では下流域の上野原町や大月市で、7世紀代の後期古墳が知られている。
富士北麓では、古墳の存在は認められないが、桂川流域では下流域の上野原町や大月市で、7世紀代の後期古墳が知られている。
大月市では、賑岡町字強瀬の子の神古墳、富浜町字宮谷の金山古墳、富浜町上鳥沢鳥沢の金山古墳のほか、駒橋にも5基の古墳(『甲斐国志』古跡之部第十六之下)があったことが記れている。
これらの内、子の神古墳については、『甲斐国志』古跡之部第16之下に、寛政7年(1795)8月13日に発掘がおこなわれ、羨道を約4.8mほど行くと、高さ1.5m、広さ0.9m余りの四方大石によって築かれた石室に至り、石室内に髑髏と、太刀脇差2振(大二尺三寸、小一尺三寸五分)、短刀1振(一尺)、箭16本、鎗・長刀の石突き2個、刀鐔1個が出土したと記されている。
同古墳は、大きな自然礫による横穴式石室を持ち、平面は胴張りの長方形を呈し、羨道と玄室の区別がない。
また、長さ約5m、幅1.2~1.6mを測り、奥壁には2mの高さからなる1枚の巨岩が使われている。
宮谷の金山古墳は、石室は子の神古墳と同様に胴張りのもので、玄室と羨道の区別がなく、長さ4.2m、幅1.6mで、石室内より鉄族10本、鉄板数個が出土し、また、鳥沢の金山古墳は、石室の規模や構造は明瞭ではないが、直刀、鰐、鉄族などが出土したとされる。
これらの古墳が所在する大月市賑岡から富浜周辺にかけての桂川流域は、笹子川、浅利川、葛野川などの支流が合流し、水量が増すと共に川幅が広がり、低位段丘面や沖積地などが形成され、また、百蔵山から扇山南麓には、緩斜面や平坦地が広がり、縄文時代以降多くの遺跡が発見されている。
ここは、東西方向に甲斐と相模・武蔵を結ぶ道が走り、南北方向には駿河や小菅、丹波山を経て武蔵と結ぶ道が十字に交わる交通の要所となっている。
上野原町内でも、神奈川県境に近接し、桂川と境川に挟まれた段丘上に位置する塚場地区に直径12mと9mの円墳2基と、前方後円墳1基(現在確認できない)があったとされ、また、鶴川を見下ろす河岸段丘の上野山地区に一辺14mと6.2mの方墳2基が報告されている。
近年、塚場より南1㎞ほどいった河岸段丘上の先端に立地する狐原遺跡の発掘調査が実施され、古墳時代後期から奈良時代前半の住居址15軒が検出された。この狐原遺跡での古墳時代から奈良時代に至る集落址の発見により、河岸段丘上の開発がこの時代にはかなり進行していたことが明らかとなった。
都留市内では、現在までのところ古墳は発見されていない。