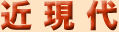
絵甲斐絹(えがいき)
 絵甲斐絹は、郡内地方の特産として文化、文政の頃から始まり、最初は絵描きが無地甲斐絹に直接描いたり、横糸をあらかじめ板に巻いて、上に絵をすり込んで製織したといわれている。
絵甲斐絹は、郡内地方の特産として文化、文政の頃から始まり、最初は絵描きが無地甲斐絹に直接描いたり、横糸をあらかじめ板に巻いて、上に絵をすり込んで製織したといわれている。
明治10年頃に経糸にすりこむようになり、20年頃は各種の顔料が使用されるようになった。絵甲斐絹は、織工が自分で経糸の織口に下から板をあてて押す位置を計って定め、型紙の上から顔料で人物や花鳥の絵を押し、顔料が乾いたら一裏分を織り、また次の絵を押しては織ってゆくもので、月に6疋織れば優秀な職工であった。この頃は絵甲斐絹がさかんに織りだされ、粋な旦那の羽織裏には、立派な絵甲斐絹がつけられていた。
絵甲斐絹は大正9年の不況時代に入って終わり、大正11年には、谷村の山一岡部工場で経糸に「解し捺染加工」を成功させ、価が安くて高級な織物として一般にも八端織物が使われるようになった。
- 【詳しく知りたい人】
- 『都留の今昔』 1978 都留市老人クラブ連合会
![]()
![]()
 絵甲斐絹は、郡内地方の特産として文化、文政の頃から始まり、最初は絵描きが無地甲斐絹に直接描いたり、横糸をあらかじめ板に巻いて、上に絵をすり込んで製織したといわれている。
絵甲斐絹は、郡内地方の特産として文化、文政の頃から始まり、最初は絵描きが無地甲斐絹に直接描いたり、横糸をあらかじめ板に巻いて、上に絵をすり込んで製織したといわれている。